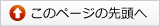学会組織図・メンバー
研究部会
- 感性情報処理・官能評価部会
- 衣服人間工学部会
- 医療労働関連MSDs研究部会
- 航空人間工学部会
- アーゴデザイン部会
- 海事人間工学研究部会
- ワーク・アーゴノミクス研究部会
- ビッグデータ人間工学研究部会
- システム大会部会
感性情報処理・官能評価部会
- 部会長:石原 正規(東京都立大学)
- 事務局:
- 活動期間:2023年4月1日~2026年3月31日
-
概要:
-
- テーマ
-
2025年度は以下の2点をテーマとする
- 感性情報処理と官能評価に関わる諸問題を多角的に取り上げ,研究者・デザイナーおよび職人・熟練者どうしの情報交換と研究の活性化,および研究内容の深度化に資する機会を提供するとともに,この領域の若手研究者およびプロの職業人・設計者の育成をはかる.
- 基礎領域研究の学びを通して,人間の知覚や認知についてのメカニズムと機能的特徴を理解する.またそれらがどの様に行動と関わっているのかについて理解を深める.実験心理学,行動科学の視点から,環境への適応に関わる諸問題の理解,解決に役立てるための機会を提供するとともに,若手研究者および実践者の育成をはかる.
-
- 手段・方法
-
感性情報処理や官能評価の基盤となる人間の感覚・知覚・感情・認知・行動等の諸特性,およびそれらの測定・評価方法や数理モデル等の研究成果や製品,サービス等の開発成果について先端的独創的な研究を紹介する.これに加えて,講演会や若手研究者を主体とした研究会や関連の研究・開発施設や工房などの見学会などを必要に応じて企画・実施する.以上の活動を通して研究者やプロの職業人・設計者相互の情報交換や交流をはかるとともに,両者の研究意欲を喚起し,人間工学に限定されない具体的かつ有益なアウトプットの創出の機会を支援する.
-
- 期待される成果
-
主に感性情報処理と官能評価に関わる研究者の関心や専門領域を共有しつつ,新たな情報や手法に刺激される機会,学ぶ機会を広範に提供することにより,特に若手研究者の裾野の拡大や関連研究領域との交流を活性化させることが期待できる.また,研究成果の実用化に伴うさまざまな困難や課題を相互に共有・議論する機会を提供し,支援することを通して,人間工学の一層の発展に資することが期待できる.
以上は,人間工学の実践における人間理解の拡大・深度化につながるものと考えられる.それらの活動過程で,これまで職人や熟練者の職能・技能としてのみ伝えられてきたモノづくりのノウハウを技術化,見える化し,それらを広く一般に提案し,還元することで,これまでの研究手法や体験,モノづくりに新たな価値(例えば感性価値や経験価値)を付加することを可能とする.
-
-
研究部会のページ:
http://www.j-erg.net/
衣服人間工学部会
- 部会長:土肥 麻佐子(文教大学)
- 事務局:
- 活動期間:2022年4月1日~2027年3月31日
-
概要:
-
- 活動テーマ
- 2012年度より継続して「グリーンファッションに関する研究」をテーマにした活動を行なっている.今年度についても,衣服のサプライチェーンの側面から,着装のあり方,廃棄ゼロを目指した衣服の構造・デザイン,衣服材料の使い方,衣服のリサイクル,フェアトレードなど,SDGs達成への貢献を視野に入れた研究活動,啓蒙活動を進めていく予定である.さらに,このような取り組みを具現化する方法の一つとして,サイズ・ジェンダー・エイジを問わないボーダーレスデザインについても考えていきたい.
-
- 活動計画(方法・手段)
-
- 幹事会 Zoomやメール,対面による幹事会の開催
-
研究例会の開催 Webと対面で2回程度開催予定
- 8月 web講演会およびwebワークショップ
- 2月 工場見学およびweb講演会
-
- 期待される成果
- 講演会,工場見学,ワークショップなどを行うことにより,グリーンファッションに関する研究・教育についての意見交換および研究交流の活性化が期待できる.また,講演会や対面での見学会の開催により,消費科学的立場より地球環境問題に対する意識の向上に貢献できると考えている. 今後これまでの活動の成果を冊子やDVDなどにまとめることについても検討したい.
-
- 研究部会のページ:
医療労働関連MSDs研究部会

- 部会長:松崎 一平(医療法人山下病院)
- 事務局:常見 麻芙(医療法人山下病院 サステナビリティ推進室)
- 活動期間:2022年6月1日~2027年3月31日
-
概要:
本研究部会は
「すべての医療従事者を守る快適な労働環境をつくる」
をパーパスに掲げ、医療従事者、学会員、企業の方々と、以下のような活動を進める。 -
活動概要:
- 医療労働関連MSDs予防ツール・教材の検討・開発
- 医療労働関連MSDsに関する教育機会の提供(研究会の開催)
- 関連学会・研究部会などの共同企画の実施および連携
- 医療労働関連MSDs軽減のグッドプラクティス・機器情報の収集と発信
- その他、本研究会趣旨に必要と思われる諸活動の実施
部会員限定の情報提供・意見交換のためのプラットフォームを通じ、学術的交流や共同研究を推進する。
年4回のセミナー開催を予定している。(適宜新着情報へアップする)部会のパーパスに賛同頂ける幅広い分野・業種の方々に、是非ご入会いただきたい。
-
研究部会のページ:
https://ergonomics-msds.org/
航空人間工学部会

- 部会長:舩引 浩平
-
事務局:
2025年度事務局 日本航空株式会社(JAL)安全推進部 - 活動期間:2023年4月1日~2028年3月31日
-
概要:
-
- テーマ
- 航空人間工学に関する知識の普及,情報の共有化を目的として,他分野を含む幅広いヒューマンファクター研究にかかわる進展,事故事例から得た人間特性及びヒューマンマシンインターフェイスに関する事故防止方策の動向を分析検討する.
-
- 方法・手段
-
-
研究例会(公開講座)の開催
日時:2025年6月18日(水)13:00-17:00(予定)
場所:野村不動産天王洲ビル2階会議室(ウィングホール)
講演:航空安全に関するテーマを予定 -
施設見学会の実施
ヒューマンファクターや各企業による安全への取り組みなどを介し,学び・知見を得ることを目的に,施設見学会を計画・実施する.可能な限り,一般公開していない施設・場所を対象とする.
また,人間工学に関する基本知識の学習,他研究部会の講演,イベントへの参加なども検討する. -
部会ホームページの運営
インターネットを使った部会ホームページを活用して当研究部会の活動内容を広く周知するとともに,活動案内の掲示や会員からの参加申し込みに活用する.また,例会講演資料の電子化への対応の利便性を向上させる. -
委員会・幹事会の開催
幹事会社が変更されるので,引継ぎを行い滞りのない委員会及び幹事会運営を行う.部会活動を円滑に行うとともに,会員の意見を部会活動に反映させるよう努める.対面式・オンライン形式の両方を活用し,効率化をはかる. -
部会活動条件の実施計画
学会誌への投稿,または学会の全国大会または支部大会での発表について検討,実施する.
-
研究例会(公開講座)の開催
-
- 期待される成果
- 例会(公開講座)及び見学会の活動を通じ,航空安全の推進に関わる官・民・学の関係者が交流する場を当部会が提供する.関係者がお互い情報を共有し,議論を行うことや,新たな人脈を構築することで航空人間工学や航空安全技術に関する動向等の知見獲得が可能となり,航空の安全の推進へ大きく貢献できるものと考える.
-
-
研究部会のページ:
http://www.jahfa.org/
アーゴデザイン部会

- 部会長:郷 健太郎(山梨大学)
- 活動期間:2023年4月1日~2028年3月31日
-
概要:
-
- 活動テーマ
- 2025年度は,フューチャーエクスペリエンス(FX)の確立を目指し,実践的な手法による事例を通じた研究活動を展開する.また,これまで取り組んできたビジョン提案型デザイン手法との関係性を明確にし,アーゴデザインの実践を深化させる.加えて,社会環境性とその実現可能性を踏まえた人間工学研究の重要性を再確認し,「ビジョンと社会実装」に関する研究と議論を,アーゴデザインの視点から継続的に推進していく.
-
- 手段・方法
-
-
フューチャーエクスペリエンス(FX)-WGの活動強化
フューチャーエクスペリエンス(FX)-WGの活動を今年度も更に強化していく.部会活動のテーマである「「ビジョンと社会実装」~ビジョン創りとこれを社会に実装するための方法論の研究~」の検討を本格化させ,新たな方法論確立に向け,ワークショップやミーティングの機会を増やし,その研究活動と方法論発表の機会を創り出す. -
フューチャーエクスペリエンス(FX)の啓発・普及活動の実施
「フューチャーエクスペリエンス(FX)」については,これまで同様に EXPERIENCE VISION 普及のためのイベントを開催する.また,フォーラムや合宿研究会,ワークショップなどの機会をとおして,「ビジョン創りとこれを社会に実装するための方法論の研究」の活動との連携を図る. -
学生会員に対する部会活動の充実
定着した学生会員制度により,学生会員の構成が固定化している.そのためコンセプト事例発表会等を通じて,これまで以上に学生の研究やデザイン活動を支援する活動の充実を図り,新たな学生会員の獲得を目指す.加えて,次世代を担う研究者やデザイン実務者の育成を強化する.
-
フューチャーエクスペリエンス(FX)-WGの活動強化
-
- 期待される効果
- アーゴデザインに関心を持つ研究者や実践者と問題意識を共有し,研究開発を協働して進めることにより,人間工学分野への新たな関与や参入の機会を創出することが期待される.とくに,フューチャーエクスペリエンス(FX)に関する議論を通じて,将来の社会や環境のあり方を展望し,人間生活を包括的にデザインするための基盤を提供することができる.これにより,人間工学分野に新たな知見と視座をもたらし,ひいては次世代の人間工学の基盤形成に寄与することが期待される.
-
- 活動予定
-
- 5月 幹事会(幹事の役割,担当行事の検討)
- 7月 FXフォーラム開催,幹事会
- 9月 コンセプト事例発表会,幹事会
- 11月 見学会開催,幹事会
- 12月 幹事会
- 1月 FXフォーラム開催(HCD_net 京都サロン合同),幹事会
- 3月 2025年度 合宿研究会,総会,幹事会
-
-
研究部会のページ:
http://www.ergo-design.org/
海事人間工学研究部会
- 部会長:村井 康二(東京海洋大学)
- 事務局:吉村健志(海上技術安全研究所)
- 活動期間:2023年4月1日~2028年3月31日
-
概要:
-
- テーマ
- 日本は海に囲まれた島国であることから,他国に比べて多くの人が海に携わった仕事に従事している.更に,仕事として関わりが無くても,非常に多くの人が趣味としてマリンレジャーを楽しんでいる.しかしながら,これら海事の分野において,人間工学を学術的に取り入れた研究や製品開発に活かした事例は現時点ではまだまだ少ない.そこで,本研究部会の活動を通して,人間工学を海事分野に広く普及させ,海事の現場に人間工学に基づき設計されたシステムや製品導入を加速させる.
-
- 手段・方法
-
-
企画セッションの提案
毎年度,人間工学会の全国大会や支部大会で本研究部会が主体となった企画セッションを行い,様々な分野の人間工学の研究者と議論を交わし,海事人間工学研究の活性化を行う.2025年度は支部大会で企画セッションを行う予定である. -
見学会の開催
2025年度においては,海事関係施設の見学会を企画し,実務者との意見交換会を企画する予定である. -
座談会の開催
海事人間工学研究部会の研究課題の一つである自動・自律化船にかかる課題等について,人間工学を専門とする研究者や技術者が討論することで,海事分野における知識・実践をメンバーに共有する. -
幹事会の開催
本研究部会の円滑な運営を図るため,毎年度2回以上の幹事会を開催する.また,コミュニケーションの頻度を増やすため,WEB会議システムも活用する.
-
企画セッションの提案
-
- 期待される効果
- 企画セッションや見学会・座談会の開催を通じて,最新の海事関連研究に関する情報を発信する.また,研究者や技術者との連携を発展させることで,更なる海事関連研究の活性化及び課題解決を図る.
-
- 研究部会のページ:
ワーク・アーゴノミクス研究部会
- 部会長:井出 有紀子(NEC)、青木 和夫(日本大学)
- 事務局:
- 活動期間:2023年4月1日~2028年3月31日
-
概要:
-
- テーマ
- 在宅勤務やオンライン会議などのオフィスワークでの新しい働き方や環境も踏まえつつ,ポストコロナ時代の働き方や定年延長や人生100年時代,多様性雇用を見据えて,働く人々の健康と安全を守るための人間工学について研究するとともに,知識の普及を図ることを目的とする.
-
- 手段・方法
-
- 第66回大会における企画セッション「高齢者の体力と運動能力」の実施
- 「年齢別に見た体力測定値」 山田クリス孝介(東海大学)
- 「高齢者を対象とした運動教室とその効果」 村木里志(九州大学)
- テレワークやモバイルワークの人間工学ガイドライン(FAQなど)の改訂
- 人間工学専門家認定機構・委員会・他部会等と連携し,高齢者や女性の雇用対策や多様な働き方を行って いる事業所の見学会の実施,またはセミナーの開催
- 日本人間工学会誌「人間工学」に開催の報告
- メールやZoom,対面による幹事会・部会の開催
- 第66回大会における企画セッション「高齢者の体力と運動能力」の実施
-
- 期待される効果
- 在宅勤務やオンライン会議などのオフィスワークでの新しい働き方に関して,今年度は,ガイドラインとしてアウトプットすることにより,社会への発信とプレゼンス向上が期待できる.また,高齢者や女性の働く環境に関しては,第66回大会の企画シンポジウム「高齢者の体力と運動能力」で,近年の高齢者の体力と運動能力についての知識と実践例を知ることによって,労働者の高齢化への対応についてより深い議論を期待できる.
-
- 研究部会のページ:
ビッグデータ人間工学研究部会
- 部会長:吉武 良治(芝浦工業大学)
-
事務局:
604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
株式会社 島津製作所 DX・IT戦略統括部 DX戦略ユニット
新家 敦(シンヤ アツシ)E-Mail: shiny【アット】shimadzu.co.jp
(【アット】は@に変えてください) - 活動期間:2025年4月1日~2030年3月31日
-
概要:
-
- 2025年度研究部会テーマ
-
- 今あるデータを活用した人間工学
- 「+人間工学」活動の開始
- 研究部会活動およびビッグデータ活用ノウハウ集
-
- 活動内容(手段・方法)
-
- 年間を通じて幹事間の情報交流を主に電子メールを用いて行う.
- 年3回の講演会・談話会・勉強会等をオンラインにて開催する.
- 汎用データの人間工学的活用の事例集をまとめる.
-
- 期待される成果
-
- データサイエンティスト他,ビッグデータを扱う人材は増加している.マーケティングやモノ作りなどで,データの解析には人間の特性を知る必要があることが多いため,それら研究者・実践者に気づきと人間工学の知識を加える,「+人間工学」活動を継続し,人間工学の普及に貢献する.
- 人間工学の視点でまとめられた汎用的なビッグデータの事例集を世の中に提供することで,人間工学を社会に普及させる.
-
- 研究部会のページ:準備中
システム大会部会
- 部会長:衛藤 憲人(東海大学)
- 事務局:
- 活動期間:
-
概要:
-
- 本会の目的
- 多種多様な分野の研究者が集い,学生や若手研究者の最初の発表の場(特に,日本人間工学会全国大会(毎年6月頃開催)・各地方支部大会前の所謂,萌芽的研究段階での発表)として好評である本学会も,四半世紀を大きく越え,今年で34年目を迎える.人間工学をシステム論的立場から研究・議論することを目的に,感性情報処理・官能評価部会,聴覚コミュニケーション部会,旧ヒトをはかる部会,旧座研究部会,旧視覚エルゴノミクス研究部会を中心として立ち上がった本部会であるが,近年,全国各地から大学関係者,企業研究者の発表も増え,医学から工学, さらには人文科学領域にわたる幅広い分野の研究者が集い,議論できる同大会は盛況である.今後も,より活発な発表の場としての役割を果たすべく,次回の大会(第34回システム大会)の企画を行なっている.
-
- 活動の内容
- 第33回システム大会(2024年度(令和六年度)大会,早稲田大学主催)をハイブリッド(対面・オンライン)にて開催した.二日にわたり行われた同大会は,のべ100名を超える参加者を集め,極めて盛況であった.特に,小規模学会の特性を活かし,十分な発表・質疑応答時間(発表時間20分,質疑応答10分)を確保した発表スタイルは,活発かつ深い議論を可能にし,来場者の方々にも極めて好評であった.今後も,同大会を通じて,学生,若手研究者にも人間工学への興味を持ってもらい,日本人間工学会会員にすべく努力する所存である.現在,次期大会(第34回システム大会,主催校未定)開催に向け,大学教員を中心とした年数回の幹事会実施を計画している.
-
-
研究部会のページ:
https://www.ergonomics.jp/TG/systemtaikai/